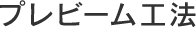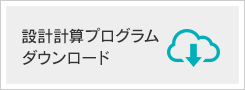Q&A集・FAQ
Q&A 集のダウンロード
Q&A 項目リスト
1.プレビーム合成桁の概要について
2.プレビーム合成桁の構造について
3.プレビーム合成桁の計画・設計について
4.プレビーム合成桁の施工について
5.プレビーム合成桁の積算について
1.プレビーム合成桁の概要について
Q1-1:プレビーム桁とは? また、その製作方法は?
Q1-2:プレビーム振興会とは?
プレビーム振興会は、プレビーム工法の発展のために、1971年に発足した組織で、会員は以下の通りです。
組織図
- (株)IHI インフラ建設
- (株)安部日鋼工業
- 川田建設(株)
- 川田工業(株)
- 極東興和(株)
- コーアツ工業(株)
- 昭和コンクリート工業(株)
- ドーピー建設工業(株)
- 日本高圧コンクリート(株)
- (株)日本ピーエス
- ピーエス・コンストラクション(株)
- 東日本コンクリート(株)
- (株)富士ピー・エス
- 協立エンジ(株)
- (株)駒井ハルテック

会員
賛助会員
Q1-3:プレビーム合成桁とは、どのような構造ですか? また、その材料は?
構造
プレビーム合成桁は、プレビーム桁を用いた合成桁をいい、通常の鋼・コンクリート合成桁と同様、鋼桁上フランジと床版コンクリートをずれ止めにより合成しています。また、鋼桁ウェブの防錆のために腹部コンクリートを打設し、鋼桁全体をコンクリートで被覆(図-1)しますが、桁高が高い場合には、鋼桁ウェブに防錆処理を行い、鋼断面とする構造(図-2)も可能です。

材料
・鋼桁
所定のソリがつけられたⅠ桁に、下フランジには角鋼ジベルを、上フランジには頭付きスタッドを設けてコンクリートと合成しています。鋼材の材質は橋梁でSM490Y・SM570材を使用し、建築でSN490B材を使用しています。
・下フランジコンクリート
設計基準強度は σck=40N/mm2 以上とし、道路橋では σck=50N/mm2 のものが多く使用されます。一般的に工場にて施工されます。
・腹部コンクリート
鋼桁ウェブを防錆するための部材で、作用力に対して抵抗断面には考慮しません。設計基準強度は床版コンクリートと同様に σck=27N/mm2 以上のものを使用します。輸送・架設時の重量低減のため床版打設前に現場で施工します。
・床版
設計基準強度は σck=27N/mm2 以上のものを使用し、道路橋では σck=30N/mm2 以上のものが多く使用されます。合成桁の床版と同様です。
Q1-4:プレビーム合成桁が適用される支間長とその桁高/支間比は?
プレビーム合成桁の適用支間長と桁高/支間比について、表-1に示します。これまでの施工実績においては、単純プレビーム合成桁の場合、支間長さとして20~40mクラスが施工総数の約4/5を占めています。近年の年間施工実績では、連続桁が半数以上を占めており、なかでも河川改修に伴う架け替えや跨線橋等に適用されるケースが多くなっています。
(※)施工実績は「施工実績データベース検索」でご確認いただけます。
また、実績集は「書籍一覧、施工実績集」のページからダウンロードできます。
Q1-5:プレビーム合成桁の特長は?
1. 桁高を低くできる
● 桁剛性が大きく活荷重たわみが小さいので、桁高に制限を受ける場合に有利です。
2. 線形に優れている
● 道路の平面線形に応じた変断面・バチ形等の構造が容易にできます。
● 鋼桁が埋め込まれているので、拡幅の処理や道路縦断に合わせた変断面桁への適用が容易です。
3. 低騒音である
●剛性が高く、質量も比較的大きいため、車両通行時の振動による騒音が少ないです。
4. 塗装の塗り替えが不要
● 鋼板がコンクリートで覆われている、または長期防錆処理を適用しているため塗り替えが
不要であり、維持管理費の低減が図れます。
5. 現場での主桁製作ヤードが不要
● 分割工法を採用することで、現場での主桁製作ヤードが不要となります。
6. 架設が容易である
● 1本当たりの架設時の重量がPC桁の1/2程度であり、かつ架設時の桁重心が低く取扱いが容易です。
7. 連続化が可能
● 連続桁への適用により、さらに経済化が図れます。
Q1-6:連続プレビーム合成桁の特長と施工実績は?
特長
1. 単純桁と比較して同支間・同桁高であれば、径間部の曲げモーメントが小さくなるので、
主桁本数を少なくでき、経済的な計画ができます。
2. 総工事費は単純桁の80% ~ 90%になります。
3. 単純桁を連ねる場合と比較して、走行性と耐震性が向上します。
4. 単純桁と同桁高であれば、支間を伸ばすことができます。
5. 単純桁と同支間であれば、桁高を低くすることができます。
6. モーメントバランスを考慮した支間割で計画することで、更に経済性が向上します。
施工実績
連続プレビーム合成桁橋の施工実績は、2025年3月末現在で320橋です。
※上部工工事費は設計条件によって、大きく変動します。
プレビーム設計計画に関するお問い合わせフォームからご連絡いただければ、
概算工事費や可能桁高の検討を行います。
Q1-7:鋼板ウェブ仕様のプレビーム合成桁とは?
鋼板ウェブ仕様とは主桁の腹部コンクリートを省略した構造です。利点として、輸送・架設時の桁重量および下部工に対する死荷重反力を低減することで、建設コストが縮減されます。平均桁高が1.0m程度以上の場合には、経済性と施工工程短縮の観点から、鋼板ウェブ仕様が推奨されています。なお、鋼桁ウェブが外部に露出されるため、適切な防錆処理を施す必要があります。
※防錆仕様は、「2.プレビームの構造 Q2-4」参照
Q1-8:プレビーム合成桁橋における分割工法とは?
Q1-10:プレビーム合成桁橋に用いられる埋設型枠(KKフォーム・KKアーチフォーム)とは?
プレビーム合成桁橋に用いられる埋設型枠には、適用部位に合わせて下図の2種類があり、工場で製作されるものです。
種類
特長
1.高い耐久性と剥落対策を備えた床版形式
2.産業廃棄物が発生しないため、環境にやさしい
3.維持管理が容易
4.型枠設置が容易で、普通作業員での設置が可能
5.型枠工の工程が短縮可能
6.簡易足場を設置した場合には、吊り足場の省略も可能(図-3)
留意点
1.型枠費用が木製型枠よりも高く、製品見積もりが必要 (問い合わせ先:協立エンジ株式会社)
2.型枠設置工の歩掛がなく、施工見積もりが必要
3.木製型枠に比べ、死荷重が若干増加
性能
1.輪荷重走行試験により、KKアーチフォームをRC床版の有効断面に含めても、押抜きせん断耐力・疲労
耐久性などの構造耐久性に関して問題ないことが確認されている。
2.塩分浸透試験により、コンクリートより優れた耐塩害性が確認されている。
3.KKフォームとコンクリートの剥離試験により、コンクリートとの付着強度が 3.3N/mm2 と高い。
( NEXCOなどの基準は 1.5N/mm2 以上)
2.プレビーム合成桁の構造について
Q2-1:プレビーム合成桁に適用する支承および落防防止システムは?
Q2-2:伸縮装置のタイプに制約はありますか?
Q2-4:鋼板ウェブ仕様の防錆仕様は?シール材の仕様は?
Q2-7:下フランジのずれ止めタイプの使い分けは?
Q2-8:プレビーム合成桁に使用する鋼桁の最大板厚は?
Q2-9:分割工法の主桁連結部付近の下フランジコンクリート端部のひずみ差対策は?
分割工法の下フランジブロック端部には、リリース時に鋼桁とコンクリートのポアソン比膨張によるひずみ差が発生します。鋼桁のフランジ幅が広いため、下フランジコンクリートは幅方向に押されコンクリートに引張力が作用します。その対策として、以下の対策を標準としています。

引張応力への対策
<方法1> 横締めプレストレスの導入
リリース時に横方向のプレストレスを載荷フレームにより与える。
鋼桁ウェブにゲビン貫通孔が必要となる。

<方法2> 以下のⅰ~ⅲを組み合わせる。
ⅰ)下面補強鉄筋の追加
ⅱ)端部の下フランジジベルを分割
ⅲ)鋼桁下フランジ側面へのひずみ差吸収材の貼付


※以下のいずれかに該当する場合、上面補強鉄筋を追加すること。
・連結部のプレビーム桁高が1.2m以上
・連結部のリリース時におけるコンクリート上面圧縮応力度10N/mm2 以上
・下フランジコンクリート幅1000mm以上
Q2-10:連結部の下フランジコンクリートのスタッドバーと高力ボルトが干渉する部分の対応方法は?
3.プレビーム合成桁の計画・設計について
Q3-1:プレビーム合成桁の標準的な形状は?
Q3-2:路面の勾配形状に合わせて床版面を折るなどの対応は可能か?
Q3-3:プレビーム桁の桁配置計画は?注意点は?
Q3-4:プレビーム合成桁の桁高と支間の関係は?最小桁高は?
Q3-5:連続プレビーム合成桁の基本的な考え方は?
連続プレビーム合成桁の考え方は、下図のように、死荷重による作用曲げモーメントの変曲点において、径間部と中間支点部の2つの領域に分けて考えます。

・径間部
死荷重曲げモーメントが正となる区間であり、構造特性が単純桁とほぼ同様と考えられるため、通常のプレビーム桁を用います。
・中間支点部
死荷重曲げモーメントが負となる区間であり、下フランジコンクリートには、作用荷重により圧縮力が作用するので、プレストレスを導入する必要はありません。
・連結部
径間部と中間支点部を連結させる区間であり、連結位置は死荷重曲げモーメントがわずかに負となる位置に設けられます。このために、連結部の下フランジコンクリートには床版自重以降の死荷重によって圧縮力が生じるのでプレストレスを導入する必要はありません。
Q3-6:プレビーム合成桁の移動量の考え方は?
プレビーム合成桁橋は、鋼桁の要素とPC桁の要素があり、移動量の設定方法が統一されていなかったため、物件ごとに異なるケースがありました。そのため、下記の設定方針をプレビーム振興会では標準としています。
1.温度移動量の考え方について
○線膨張係数
合成桁であるため 12x10-6/℃ とする。
○温度変化範囲
温度変化範囲は、余裕を考慮し「鋼橋(上路橋)」を標準とする。
ただし、鋼桁ウェブの防錆仕様に応じて、温度範囲を下記としても良い。
・腹部コンクリート仕様
「コンクリート橋の温度範囲」 -5 ~ +35℃(普通の地方)40℃変化 移動量=0.48L
・鋼板ウェブ仕様
「鋼橋(上路橋)の温度範囲」 -10 ~ +40℃(普通の地方)50℃変化 移動量=0.6L
2.クリープ・乾燥収縮による移動量の考え方について
鋼桁が内部に合成されているため、桁軸方向の変位は微小で無視できる程度であり、クリープ・乾燥収縮による桁軸方向の移動量は考慮しない。ただし、クリープ・乾燥収縮に伴うたわみ変化については考慮する必要がある。
3.伸縮量簡易算定式について
鋼桁と床版の合成作用を考慮する構造であるため、道示の解説の伸縮量簡易算定式は「鋼橋」を標準とします。線膨張係数やクリープ・乾燥収縮が異なる「RC橋」「PC橋」の簡易算定式は使用しない。上記の腹板仕様の温度変化範囲を考慮し、簡易算定式の温度変化による伸縮量を変更することも可能です。
Q3-7:支承照査に用いる活荷重の回転角の適用は鋼桁かコンクリート橋か?
Q3-8:添架物設置に伴って横桁を切欠く場合の注意点は?
Q3-9:プレビーム合成桁の輸送部材長の設定方法は?
Q3-10:枝桁の取付構造、および、その解析方法は?
枝桁の取付構造
枝桁は、主桁の上フランジとウェブに仕口を設け高力ボルトで連結します。主桁下フランジ側には下フランジコンクリートがあるため、主桁下フランジと枝桁下フランジについては連結しないのが一般的な形状です。
枝桁の解析方法
枝桁仕口部の剛性は非常に小さく、枝桁が負担する主桁系の断面力は微小です。全体格子解析の骨組みモデルに枝桁を考慮した場合、主桁の負担断面力が過小に評価される傾向にあります。計算の簡易化を図るため、格子解析には枝桁をモデル化しないことが望ましい。枝桁に作用する断面力は、主桁取り付け部と支点で支持された単純梁として設計します。主桁には枝桁からの反力を集中荷重として載荷させます。
Q3-11:3径間以上の連続桁において中間支点の支承を固定とした場合の不静定力の取り扱いは?
Q3-12:桁端部の床版設計時の活荷重は2倍とするのか?
Q3-14:埋設型枠(KKフォーム・KKアーチフォーム)の断面形状の選定方法は?
以下に示すように、適用部位や主桁間隔に応じて製品を選定してください。床版コンクリートの底板埋設型枠(KKアーチフォーム)として使用する場合は、応力検討を行った上で板厚を選定する必要があります。詳細については、製造メーカー(協立エンジ株式会社)にお問い合わせください。
Q3-15:埋設型枠(KKフォーム・KKアーチフォーム)は、設計断面に考慮できるのか?
設計計算上は、KKフォーム・KKアーチフォームの構造を考慮して下記のように取り扱うことが可能です。
①床版の設計について
・KKアーチフォームの突起部厚のみ、設計上のRC床版厚に含める。
・床版下面のかぶりは、KKアーチフォーム平板部上面から鉄筋下面までとする。
②主桁の設計計算について
・KKアーチフォームの突起部厚のみ、主桁の有効断面に含める。
これは、安全余裕を考慮し、目地部における圧縮応力の伝達を無視するためである。
・合成桁設計上のコンクリート上フランジ厚は、KKアーチフォームを控除した
「床版全厚-KKアーチフォームの平板部厚」とする。
③横桁の設計計算について
・KKフォームの突起部厚のみ、横桁の有効断面に含める。
横桁の側型枠にKKフォームを使用した場合、目地部はせん断抵抗の断面厚に考慮
できないため、平板部厚は有効断面に含めない。
Q3-16:プレフレクション時の残留たわみとは?
Q3-17:プレビーム合成桁の計算プログラムは?
プレビーム合成桁の応力計算順序は「プレビーム合成桁橋設計施工指針」の付録に詳細式が紹介されています。プレビーム詳細設計プログラムの概要およびダウンロードはこちら
プログラムの概要
・本プログラムは、プレビーム合成桁橋のRC床版の設計、構造解析、主桁断面計算、横桁設計、
その他部材の設計・照査までを一括で行う無料の設計計算ツールです。
・基本条件を入力すればプログラム内部で各種データを自動設定しますので、初期値の検討作業の省力化が
可能です。ここで、自動設定されたデータは設計者の判断で任意に変更することが可能です。
また、計算結果に対するチェック機能がありますので、照査漏れを防ぐことができます。
・設計計算のみに対応し、図面・数量には対応していません。
プログラムの適用範囲
プログラムの計算項目
1. 設計断面位置・主桁本数・主桁間隔・主桁形状・横桁本数・横桁幅の自動設定
2. 床版の設計
3. 荷重強度の算出
4. 合成前荷重による断面力、変位および反力の算出(平面骨組解析)
5. 合成後荷重による断面力、変位および反力の算出(平面格子解析)
6. 断面力、支承反力および下部工設計用反力の集計
7. 曲げモーメント図およびせん断力図の作成
8. 計算主桁の自動選定
Q3-18:プレビーム合成桁橋の概略工費、概略設計は?
プレビーム合成桁橋の工費は、主桁高、主桁形状により、大きく変化します。
そのため、概算工事費(万円/m2)をグラフ化した資料はなく、概略設計にて、概略工費を算出しています。
概略設計はこちらより、設計条件を問い合わせいただければ無料で対応しています。
4.プレビーム合成桁の施工について
Q4-5:分割工法の場合の桁連結部の局部プレストレスの導入方法は?
Q4-6:プレビーム合成桁の架設は、 どのような工法が一般的ですか?
1. 部材ごとのトラッククレーンベント工法
桁下の使用が可能な場合に採用され、通常最も経済的となる架設工法です。工場で製作した部材を現地に輸送し、この桁をトラッククレーンにてベント上に架設し、各部材を連結します。

2. トラッククレーンによる一括架設
長時間にわたり桁下の使用ができず、短時間での架設が要求される場合や河川内にベントを設置できないときに採用される架設工法です。工場から搬入した部材を地組みにより1本物にした後、大型のトラッククレーンにて一括架設します。

3. 架設桁架設
河川上などで桁下の使用が困難な場合に採用される工法です。工場から搬入した部材をトラッククレーンにて架設桁上に仮置きし、連結した後、門構あるいはトラッククレーン等にて横取り架設します。

Q4-7:連続桁施工時のベントの必要性は?
Q4-10:桁架設後の床版横桁工に必要な足場空間高は?
Q4-11:プレビーム合成桁橋の下フランジコンクリートに使用する標準的なコンクリート配合は?
Q4-12:プレビーム合成桁橋の腹部コンクリートに使用する標準的なコンクリート配合は?
5.プレビーム合成桁の積算について
Q5-1:プレビーム合成桁橋の詳細設計歩掛は?
プレビーム合成桁橋の詳細設計に関する設計歩掛は設定されておらず、下記の対応の実績があります。
①見積り調査
②鋼・合成鈑桁橋相当と仮定して、鋼・合成鋼鈑桁橋の歩掛を採用
③PCポストテンションT桁橋相当と仮定して、PCポストテンションT桁橋の歩掛を採用
④PCポストテンションT桁橋の歩掛に鋼・合成鈑桁橋の歩掛を補正して合算
プレビームの構造は、合成鈑桁にプレストレスされた下フランジコンクリートを合成させた構造です。主桁の構造形状は、ほぼ合成鈑桁相当となっており上記②として設定される事例があります。
また、積算上の分類がPC橋であるため、上記③として設定される場合があります。
上記④は必要な構造設計項目を考慮して算出したケースであり内訳を下記に示します。
Q5-2:プレビーム桁の積算方法は?
分割工法が標準となっており、工場にてプレビーム桁が製作されるため、製品費として見積り扱いとなります。
現場架設以降の施工歩掛は、「土木工事標準積算基準書」(国土交通省)に積算歩掛が設定されています。